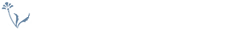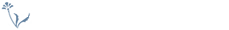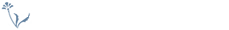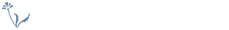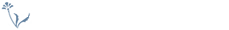新思潮 No.126 2014年5月号①
| 足許の鳩と真新しい春を | 岡田俊介 |
| 散歩の途中であろうか、足許に寄ってきた鳩を見ているうちに、この小さな生きものの命の温もりが、作者のたましいに伝わってきたのだ。そんな命の高揚感を以て、作者は清新の気を脹らませながら、春を迎えようとしているのだ。一病を得て、辛い時を過していた岡田代表だけに、この向光性に導かれた秀吟を、『新思潮』の一員として悦びたい。〈春暁に敢えていびつな馬かざる〉の句も同様である。 〈細川不凍〉 | |
| 朧夜を残して青い塔消える | 岡田俊介 |
| 足許の鳩と真新しい春を | 岡田俊介 |
| 鳩の気ぜわしい動きは、我々には見えぬ春の存在を教えている。見えていないものを青い塔として、しがみつこうとしてみるのだが、そこには朧夜があるばかり。しかし、それは儚い感触ではなく、確かな朧夜の手応えを残しているのだ。 〈矢本大雪〉 | |
| 如月を棚から下ろし御雛様 | 福田文音 |
| 北国の冬で最も酷しいのが如月だ。暮しに重くのしかかるその如月に別れを告げ、心は春の色調に染まりつつ、御雛様を飾るのだ。隠喩法を用いた「如月を棚から下ろし」の語句が心の切り換えを鮮やかに描出していて、十七音表現者としての作者の技量を見た。作品の底流に在るのは心根の優しさで、文音作品の母体でもある。 〈細川不凍〉 | |
| 蒟蒻のように考え込んでいる | 古谷恭一 |
| 「考え込む蒟蒻□□□□□□□□」という二句一章の姿が想定され、なぜそうならないのかという疑問も生まれるのだが、そこに川柳の不気味な強靭さがあるのかもしれない。自分の呟きだけで成立させる作品群は、あえて書いていない作品の余白というよりは、その先に対立しているもう一つの世界(書かれていない「取り合わせのもう一方」)を暗示させることで、新しい川柳の取り合わせや、モンタージュを提案していそうだ。 〈岡田俊介〉 | |
| 青眼に醒め億光年を得る蜻蛉 | 山内 洋 |
| 親しい人が訪れたとき、喜んで迎える目つきをいう〝青眼〟の言葉が、句を支配しているだろう。蜻蛉は青眼に醒めたが故に億光年、ほぼ永遠のいのちを得たという、一種の童話を書いて、深淵にいる蜻蛉を描いている。山内ならではのイメージの広がりである。 〈岡田俊介〉 | |
| 雲梯も古りて記憶の樹となれり | 杉山夕祈 |
| 雲梯ほど、小学生の頃の記憶と密接なものはない。なぜ、どんな目的で存在したのだろう。卒業とともに、雲梯は忘れ去られ、今は一本の樹があったかのように、漠然と記憶の底にのこされている。しかし、手触りだけはいつまでも消えてはいない。 〈岡田俊介〉 | |
| 梅一輪出合いがしらの声に似て | 北山 茂 |
| 梅をこの作者はこのように表現した。句から梅の咲き始めの頃の様子が見えてくる。梅一輪が凜と咲き、それを思わぬところで見つけたのなら、このような喩えになるだろう。しばらく会わなかった人に出会ったときの心情とどこか似ているものを感じたのであろう。それほど早春に咲く新鮮な梅なのだ。喩を使えば句はいきいきとしてくる。 〈岡田俊介〉 | |
| ずっとずっと少女 さくら生まれにて | 月野しずく |
| さくらの季節のうきうきした感じがよく出ている作品群だ。ことに〝ずっとずっと少女〟の表現に、はしゃいだ気分がよく出ている。この句では〝さくら生まれ〟の言葉が新鮮だ。三月生まれ、四月生まれと同じような使い方の〝さくら生まれ〟であり、それゆえにその人がずっと少女で居られるという繋がりの発見もある、大胆な表現だ。さくらの薄紅の初々しさはどこかで少女に繋がり、大人の女性をも初々しくするものに思えてくる。
〈岡田俊介〉 |
|
| 白光の何に近づくわれの鈴 | 松田ていこ |
| 荒塊が憑依している寒夕焼 | 矢本大雪 |
| 吹雪いては墨職人の爪先に | 山崎夫美子 |
| 雪。雪。。雪。。。栞いらずのミステリー | 古俣麻子 |
| 生きているゾ暗渠を奔る水となり | 御供田あい子 |
| 群れ飛ぶ鳥に雪つぎつぎと亡命せり | 西条眞紀 |
| さまざまな刻の形になって咲く | 潮田 夕 |
| 背を送るゼブラゾーンにたまる雪 | 吉田州花 |
| 転寝の夢の中まで冬怒涛 | 鮎貝竹生 |
| 月の窓ほどいて君を描きなおす | 澤野優美子 |
| 柚最中ひとつ手に取り夕闇へ | 寺田 靖 |
| 雛飾り遠い時間のあとさきに | 大橋あけみ |
| 顔も声も知らないははをどう詩(うた)う | 青野みのる |
| 満ち欠けの合間どんぶり飯を食う | 高橋 蘭 |
| いいえその時ボクは雲でした | 岩崎眞里子 |
☆ NO.126の読みもののご案内
・エッセイ「創作の原風景」 岩崎眞里子
・神戸研修句会合評会より H25.11.23
・随筆「風をつかまえに」 古俣麻子
・エッセイ「創作の原風景」 岩崎眞里子
・神戸研修句会合評会より H25.11.23
・随筆「風をつかまえに」 古俣麻子
※神戸研修句会合評会の模様は近くホームページでご紹介します。
2014.5.17