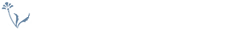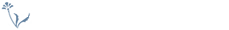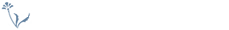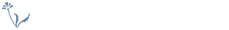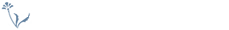琳琅 No.160 2020年1月号より②
| 白日夢ゆらゆら茶葉の開くまで | 氈受 彰 |
| ティーサーバーに紅茶の茶葉と熱湯を注ぎ、黄金の液体と化してゆく過程をじっと見つめていると、香りと共に、次第に「白日夢」の世界へと落ちてゆく。この白日夢は、「茶葉の開くまで」であり、数分後には夢から現実へ引き戻されるのだ。紅茶であれ緑茶であれ、お茶を入れるという日常の行為を切り取って、そこから非日常へと昇華させ、心地良く余情性のある仕立てとしている。〈吉見恵子〉 | |
| 葡萄ひとつぶ宗教画から零れ | 佐々木彩乃 |
| とある美術館で、作者は一枚の宗教画に魅せられた。その絵に見入っているうちに、中に描かれていた葡萄のその一粒に視線は集中した。一粒の砂の中にも宇宙はある、と書いたのは英国の詩人。ならば一粒の葡萄に、夢や希望を見出しても不思議ではない。さらに見入っているうちに、その一粒が自分の手許の方に零れ落ちてきたではないか。その瞬間、作者に創造のスイッチが入った。〈細川不凍〉 | |
| 尊厳と言ってしまえば水鏡 | 姫乃 彩愛 |
| 今までに「水鏡」の句は何度も見てきたが、この句ほど心的インパクトのあるものはなかった。水鏡に映った自分の顔を視ているうちに、頭を過ぎったのは「尊厳」という言葉。しかし、それを言ってしまうと、次に続くのは"尊厳死"だ。グサッと胸に突き刺さる内容なのだ。本来の自分の顔が映る水鏡を、と願ってやまない。〈細川不凍〉 | |
| 言いおいて遠のく背なを蔦もみじ | 岩崎眞里子 |
| 「蔦もみじ」とは紅葉した夏蔦のことで、基本的に常緑の冬蔦とは別物。この句は、言い置いて遠のいて行く背なを、いつまでも見送っている蔦もみじの視線が感じられる。つまり、「蔦もみじ」は隠喩であり、一連から両親と思われる。長らく子の背中を見守って来た両親が、子の言い置いた言葉を反芻しつつ、祈るように見送っているのだ。〈吉見恵子〉 | |
| 聞き役にまわろうと少し引く膝 | 越智ひろ子 |
| 「少し引く膝」に、難しい話を聞く体勢のリアリティが生まれた。聞き役に徹し、どんな話も受け止めようとする決意が感じられる。話を聞く時の何気ない動作を鋭く描き、作品を生き生きとさせている。〈吉見恵子〉 | |
| どこまでもけものと捜す空の青 | 松田ていこ |
| 日本昔話に登場するような人間にとってフレンドリーな「けもの」が想像される。近年は都市化政策の影響で、生きものたちの楽園である"里山"は減少するばかり。それに伴い、けものたちの行動範囲は限定され、人間との関係はギクシャクしたものになる。そんな状況を嘆くかのように、作者の内から出た言葉は痛く響く。〈細川不凍〉 | |
| 駅前に解かれて以来歳月は | 松井 文子 |
| 音のして水輪の連鎖水映す | 望月 幸子 |
| 噴水の向うに白い今あふれ | 鮎貝 竹生 |
| 飛ぶことを忘れて地上の蜜に酔い | みとせりつ子 |
| 亡夫に鈴(りん)打ち鳴らしては迎えを返す | 西条 眞紀 |
| 秋を生きむらさき色をいそぎ足 | 伊藤 寿子 |
| 溺死する茶碗を水に浸けておく | 新井 笑葉 |
| 合鍵をいっぱい撒いて母ひとり | 伊藤 礼子 |
| 雨粒のひとつきのうの終着駅 | 立花 末美 |
| 阿蘇神社まだ半身は癒えぬ傷 | 松村 華菜 |
| 難題を晴らす雲ない蒼い空 | 重田 和子 |
| 期することあって螺旋をかけのぼる | 野邊富優葉 |
2020.2.10